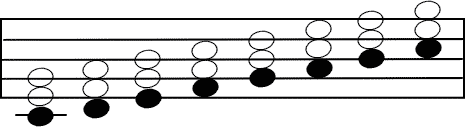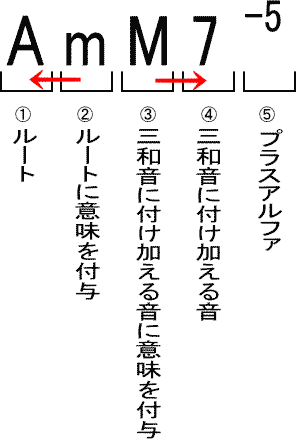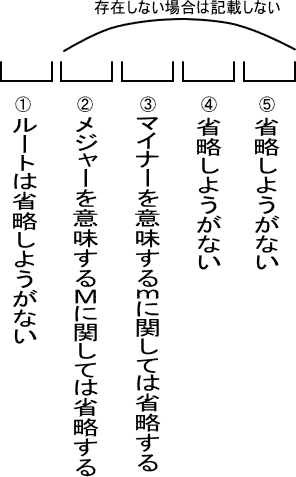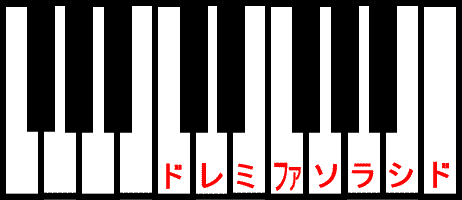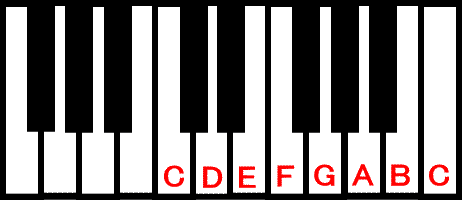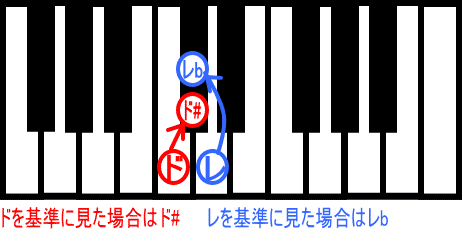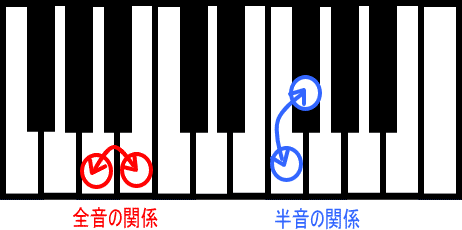嶌曇嬋島嵗戞巐夞僥僉僗僩
慜夞傑偱偵4偮偺挷偵偮偄偰偍榖傪偟傑偟偨
悽偺拞偵懚嵼偡傞妝嬋傎傏慡偰偑偙偺挷偺偄偢傟偐偵婎偯偄偰弌棃偰偄傑偡
偦偺挷偵偼丄偦偺挷偵揔偟偨榓壒偲偄偆偺偑懚嵼偟傑偡
偙偺榓壒偼婎杮揑偵丄妝嬋偑婎偯偄偰偄傞壒奒偵偁傞壒偱宍惉偝傟偰偄傑偡
嵟傕娙扨側椺偲偟偰壓偺恾傪尒偰傒傑偟傚偆
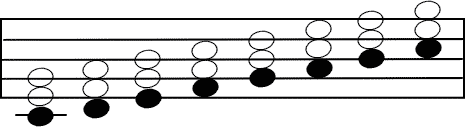
僪儗儈僼傽僜儔僔僪偲暲傫偩壒晞偺忋偵丄2偮偺壒傪摨偠奒抜忬偵暲傋偨恾偱偡
偙偺榓壒偼摉慠側偑傜丄堦偮傕仈傗侒偺晅偐側偄僴挿挷偵偁傞壒偩偗偱宍惉偝傟偨榓壒偵側偭偰偄傑偡
偙傟偑丄僴挿挷偵揔偟偨榓壒偲偄偆偙偲偵側傝傑偡
偪側傒偵忋偺恾偱偼3庬椶偺宍偺榓壒偑搊応偟偰偄傑偡
挿嶰榓壒丄抁嶰榓壒丄尭嶰榓壒偺3庬椶偱偡
偙傟偵憹嶰榓壒傪壛偊偨崌寁4庬椶偺榓壒偺偙偲傪乽庡梫嶰榓壒乿偲屇傃傑偡
偦偟偰丄偙偺庡梫嶰榓壒偼慡偰嬁偒偑鉟楉側榓壒偲偄偆堄枴偱乽嫤榓榓壒乿偲屇偽傟傑偡
偱偼丄幚嵺偵偦偺榓壒偑偳偆偄偆拞恎傪帩偭偰偄傞偺偐傪尒偰偄偔偙偲偵偟傑偟傚偆
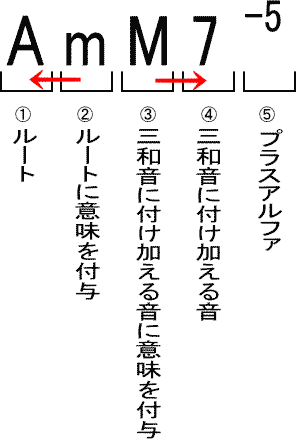 |
丂榓壒傪昞傢偡偺偵曋棙側傕偺偑丄僐乕僪偲屇偽傟傞
丂傾儖僼傽儀僢僩傗悢帤傪暲傋偨嵍恾偺傛偆側暥帤楍偱偡
丂僐乕僪亖榓壒偺偙偲側偺偱偡偑丄偙偆偄偭偨暥帤楍偺偙偲傪屇傇応崌偼
丂乽僐乕僪乿偲屇偽傟傞偙偲偑懡偄偱偡
丂偝偰丄嵍恾傪尒偰偔偩偝偄
丂慡偰偺僐乕僪偼偙偺暲傃曽偱婰嵹偝傟偰偄傑偡
丂丂丂丂嘆婎弨偲側傞壒乮儖乕僩乯
丂丂丂丂嘇偦偺儖乕僩偵堄枴傪帩偨偣傞堊偺傾儖僼傽儀僢僩
丂丂丂丂嘊晅偗壛偊傜傟傞壒偵堄枴傪帩偨偣傞堊偺傾儖僼傽儀僢僩
丂丂丂丂嘋晅偗壛偊傜傟傞壒偑壗偺壒側偺偐傪帵偡悢帤
丂丂丂丂嘍嵟屻偵曗懌傗僾儔僗傾儖僼傽傪峴偆偨傔偺昞婰
丂側偺偱丄僐乕僪傪撉傓応崌偵偼
丂丂丂丂嘆仺嘇仺嘋仺嘊仺嘍
丂偺弴偵尒偰撉傓帠偵側傝傑偡
丂傑偩壗偺偙偲偐暘偐傜側偄偲巚偄傑偡偑丄僐乕僪偼偙偆偄偆峔惉偵
丂側偭偰偄傞傫偩偲偄偆偙偲偩偗棟夝偟偰偔偩偝偄
丂幚嵺偺撪梕偺愢柧偼偙傟偐傜峴偄傑偡偺偱丄暘偐傜側偔偰傕
丂峇偰傞昁梫偼偁傝傑偣傫 |
|
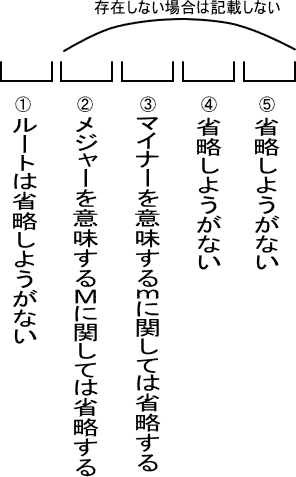 |
丂撪梕偺愢柧偵擖傞慜偵丄僐乕僪偺宍偺傕偆堦偮偺摿挜傪
丂愭偵妎偊偰偟傑偄傑偟傚偆
丂嵍恾傪尒偰偔偩偝偄
丂愭傎偳偺嘆乣嘍偺昞婰偱偡偑丄婰嵹傪徣棯偱偒傞応崌偑偁傝傑偡
丂愨懳偵徣棯偟傛偆偺側偄偺偼嘆偺傒偱偡
丂丂丂嘇偼屻傎偳愢柧偡傞儊僕儍乕傪堄枴偡傞M偵尷傝
丂丂丂丂丂徣棯偡傞偙偲偑弌棃傑偡
丂丂丂嘊偼懚嵼偟側偄応崌偲儅僀僫乕傪堄枴偡傞倣偵娭偟偰
丂丂丂丂丂徣棯偡傞偙偲偑弌棃傑偡
丂丂丂嘋偼懚嵼偟側偄応崌偵偼徣棯偡傞偙偲偑弌棃傑偡
丂丂丂嘍懚嵼偟側偄応崌偵偼徣棯偡傞偙偲偑弌棃傑偡
丂堦捠傝丄嵶偐偄撪梕傪愢柧偟廔傢偭偨偁偲偵丄傕偆堦搙
丂偙偺愢柧傪峴偄傑偡
丂偦偙偱丄棟夝偑弌棃傞偲巚偄傑偡偺偱丄崱偼乽偳偆偄偆偙偲偩傠偆丠乿
丂偲偄偆媈栤傪摢偵抲偒偮偮恑傓偙偲偵偟傑偡 |
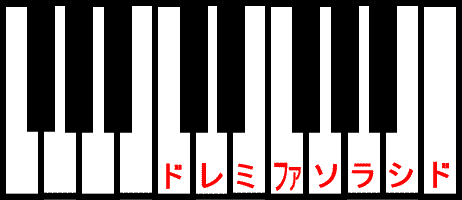
忋恾偼僺傾僲側偳偺尞斦偵僪儗儈僼傽僜儔僔僪偲彂偒崬傫偩傕偺偱偡
偙偺僪儗儈僼傽僜儔僔僪偼僀僞儕傾岅偺撉傒側偺偱丄偦傟傪塸岅昞婰偵側偍偟傑偡
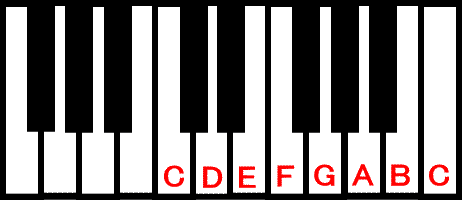
偡傞偲丄偙偆偄偆昞婰偵側傝傑偡
愭傎偳偺儖乕僩偼丄傑偝偵偙偺傾儖僼傽儀僢僩昞婰偟偨壒傪巜偟傑偡
偮傑傝丄E偲偄偊偽儈偺偙偲偱偡偟
F偲偄偊偽僼傽偺偙偲偱偡
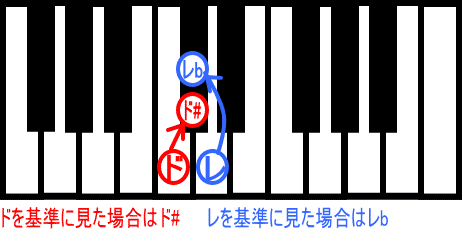
師偵忋偺恾傪尒偰偔偩偝偄
尞斦偼敀偄尞斦偩偗偱偼側偔崟偄尞斦偑搊応偟傑偡
妝晥摍偱崟偄尞斦偵偁偨傞壒偑搊応偡傞応崌丄仈傗侒偲偄偆婰崋偑巊傢傟傞偙偲偑懡偄偺偱偡
偙偺仈傗侒偺堄枴傪傑偢妎偊偰偟傑偄傑偟傚偆
尞斦偺恾偱尒傞偲暘偐傝傗偡偄偺偱丄尞斦偺恾傪巊偭偰愢柧偟傑偡偑
僊僞乕偱傕僩儔儞儁僢僩偱傕儕僐乕僟乕偱傕壗偱傕摨偠偱偡
忋恾偺尞斦偵僪偲儗偺壒偑彂偐傟偰偄傑偡偑
僪偲儗偺娫偵偼崟偄尞斦偑偁傝傑偡
偙偺僪偲椬傝崌偆崟偄尞斦
偙傟傪昞傢偡応崌偵丄僪傪婎弨偵尒傟偽乽僪偺仈乮僔儍乕僾乯乿偲側傝
儗傪婎弨偵尒傟偽乽儗偺侒乮僼儔僢僩乯乿偲側傝傑偡
偮傑傝丄仈偲偄偆偺偼丄敿壒崅偄壒傪堄枴偡傞婰崋側偺偱偡
斀懳偵僼儔僢僩偼敿壒掅偄壒傪堄枴偡傞婰崋偱偡
偝偰丄偙偙偱怴偨偵扨岅偑搊応偟傑偟偨丄乽敿壒乿偰壗丠
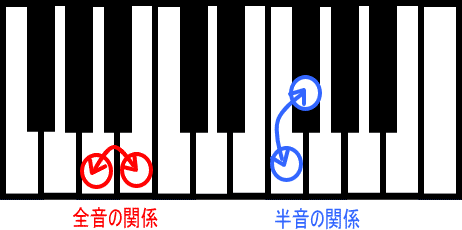
偱偼傑偢忋偺恾傪尒偰偔偩偝偄
愭傎偳偺傛偆偵椬傝崌偆壒偺娭學偺偙偲傪敿壒偺娭學偲尵偄傑偡
偦偟偰丄僪偲儗偺傛偆側2偮椬偺壒偺娭學傪慡壒偲尵偄傑偡
偦傟埲奜偺嫍棧傪昞傢偡応崌偵偼偳偆偟傑偟傚偆丠
敿壒3偮傗丄2壒敿乮慡壒俀偮偲敿壒侾偮乯偲偄偭偨尵偄曽傪偡傞偙偲傕偁傝傑偡
僇儔僆働偺傛偆偵+3傗-4側傫偰尵偄曽傪偡傞偙偲傕偁傝傑偡
偟偐偟丄偦傟偩偗偱偼傗偼傝壒妝傪偡傞偵偼晄曋偱偡
偦偙偱搊応偡傞偺偑乽搙乿偲偄偆扨岅偱偡
壓偵堦棗偵傑偲傔傑偟偨
偦偟偰丄偦偺拞偱傕昁偢妎偊偰梸偟偄嫍棧乮搙乯偵娭偟偰偼愒帤偱婰嵹偟偰偁傝傑偡
偙偺愒帤偺晹暘偼丄偙傟偐傜偺儗僢僗儞偱搊応偡傞偙偲偵側傞偺偱昁偢妎偊偰壓偝偄
偦傟埲奜偺晹暘偼丒丒丒暿偵妎偊側偔偰傕崲傝傑偣傫乮徫乯
| 搙 |
堦 |
擇 |
嶰 |
巐 |
屲 |
榋 |
幍 |
敧 |
柤
徧 |
姰
慡
堦
搙 |
憹
堦
搙 |
抁
擇
搙 |
挿
擇
搙 |
憹
擇
搙 |
尭
嶰
搙 |
抁
嶰
搙 |
挿
嶰
搙 |
憹
嶰
搙 |
尭
巐
搙 |
姰
慡
巐
搙 |
憹
巐
搙 |
尭
屲
搙 |
姰
慡
屲
搙 |
憹
屲
搙 |
尭
榋
搙 |
抁
榋
搙 |
挿
榋
搙 |
憹
榋
搙 |
尭
幍
搙 |
抁
幍
搙 |
挿
幍
搙 |
尭
敧
搙 |
姰
慡
敧
搙 |
敿
壒
偺
悢 |
侽 |
侾 |
侾 |
俀 |
俁 |
俀 |
俁 |
係 |
俆 |
係 |
俆 |
俇 |
俇 |
俈 |
俉 |
俈 |
俉 |
俋 |
侾侽 |
俋 |
侾侽 |
侾侾 |
侾侾 |
侾俀 |
幚
椺 |
崅
偄
壒 |
僪 |
僪
仈 |
儗
侒 |
儗 |
儗
仈 |
儈
侒
侒 |
儈
侒 |
儈 |
儈
仈 |
僼傽
侒 |
僼傽 |
僼傽
仈 |
僜
侒 |
僜 |
僜
仈 |
儔
侒
侒 |
儔
侒 |
儔 |
儔
仈 |
僔
侒
侒 |
僔
侒 |
僔 |
僪
侒 |
僪 |
掅
偄
壒 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
僪 |
挿嶰榓壒乮儊僕儍乕乯
偱偼丄傑偢偼挿嶰榓壒偵偮偄偰夝愢偟傑偡
挿嶰榓壒偺偙偲傪塸岅偱偼乽儊僕儍乕僐乕僪乿偲尵偄傑偡
偱偼丄嵟弶偼C偺儊僕儍乕僐乕僪傪椺偵尒偰偄偒傑偟傚偆
儊僕儍乕僐乕僪偼儖乕僩傪婎弨偵挿嶰搙偺壒+姰慡屲搙偺壒偱宍惉偝傟傞榓壒偱偡
側傫偺偙偭偪傖丠偱偡偹倵
偱偼愭傎偳偺搙偺堦棗傪尒側偑傜峫偊偰偔偩偝偄
C偮傑傝僪偺壒偑愭傎偳偺堦棗偱傕幚椺偱偺婎弨偵側偭偰偄傑偡
偱偼丄挿嶰搙偺偲偙傠偵偁傞壒偼壗偱偟傚偆偐丠
挿嶰搙偺偲偙傠偺幚椺傪尒傑偡偲
掅偄壒乮偮傑傝婎弨乯偑僪偵懳偟偰丄崅偄壒乮婎弨偐傜傒偰挿嶰搙偵偁傞壒乯偼儈偺壒偵側偭偰偄傑偡
摨偠傛偆偵姰慡屲搙偺壒偼丒丒丒僜偺壒偵側偭偰偄傑偡
偮傑傝丄婎弨偺乽僪乿+挿嶰搙偺乽儈乿+姰慡屲搙偺乽僜乿
僪儈僜偲偄偆榓壒偑C偺儊僕儍乕僐乕僪偲偄偆偙偲偵側傝傑偡
偱偼A偺儊僕儍乕僐乕僪側傜偽偳偆偱偟傚偆丠
儖乕僩偑儔側偺偱丄愭傎偳偺堦棗偺幚椺偼巊偊傑偣傫
巆擮側偑傜帺暘偱悢偊傞偟偐偁傝傑偣傫偹
偙偆偄偆嬶崌偵壒偺嫍棧傪峫偊傞偺偵昁梫偵側傞偺偑丄愭傎偳偺堦棗偱愒帤偱彂偄偨晹暘側偺偱偡
側偺偱丄妎偊傞傛偆偵偟偰壓偝偄
幚嵺偵夝摎傪尵偄傑偡偲
儖乕僩亖儔
挿嶰搙亖僪仈
姰慡屲搙亖儈
偵側傝傑偡
暘偐傝偵偔偄恖偼丄僺傾僲偺尞斦傗僊僞乕偺僼儗僢僩偺悢偱敿壒偺悢偐傜妋擣偟偰傒偰偔偩偝偄
偙偺儊僕儍乕僐乕僪偺屇傃曽偱偡偑
C儊僕儍乕僐乕僪
偲偄偆嬶崌偵尵偭偰傕戝忎晇偱偡偟
扨偵C僐乕僪
偲尵偭偰傕戝忎晇偱偡
偦偟偰丄偙偺C儊僕儍乕僐乕僪傪彂偔応崌
C偵儊僕儍乕傪堄枴偡傞M傪偮偗偰
CM
偲彂偔偺偑杮棃偺堄枴偲偟偰偼惓偟偄偺偱偡偑
愭傎偳偺徣棯偺榖偺嘇偺儖乕儖
嘇偺埵抲偵偔傞傾儖僼傽儀僢僩偱儊僕儍乕傪堄枴偡傞M偵娭偟偰偼徣棯偟偰婰嵹偡傞
偲側偭偰偄傑偡
偦偟偰嘊乣嘍偵娭偟偰偼丄C儊僕儍乕僐乕僪偵偼懚嵼偟傑偣傫
側偺偱徣棯偟傑偡
偡傞偲
C
偩偗偑巆傝傑偡
偮傑傝丄僐乕僪傪昞婰偡傞応崌C儊僕儍乕僐乕僪偼扨偵乽C乿偲偩偗婰嵹偝傟傞偺偱偡
抁嶰榓壒乮儅僀僫乕乯
抁嶰榓壒偺偙偲傪塸岅偱偼乽儅僀僫乕僐乕僪乿偲尵偄傑偡
偱偼丄愭傎偳偲摨偠傛偆偵C偺儅僀僫乕僐乕僪傪椺偵尒偰偄偒傑偟傚偆
儅僀僫乕僐乕僪偼儖乕僩傪婎弨偵抁嶰搙+姰慡屲搙偱宍惉偝傟傞榓壒偱偡
摨偠傛偆偵堦棗傪尒偰傒傑偟傚偆
儖乕僩亖僪
抁嶰搙亖儈侒
姰慡屲搙亖僜
偲側偭偰偄傑偡偹
偙偺僪儈侒僜偲偄偆榓壒偑C偺儅僀僫乕僐乕僪偵側傝傑偡
偙偙偱愭傎偳偺儊僕儍乕僐乕僪偲斾妑偟偰傒偰偔偩偝偄
堘偄偼偳偙偵偁傝傑偡偐丠
偦偆丄儈偐儈侒偐偺堘偄偟偐偁傝傑偣傫
C偺儅僀僫乕僐乕僪傪屇傇帪偵偼
C儅僀僫乕
偲偦偺傑傑屇傃傑偡
偦偟偰丄偙偺儅僀僫乕僐乕僪傪婰嵹偡傞応崌偼
C偵儅僀僫乕傪堄枴偡傞彫暥帤偺m傪偮偗偰
Cm
偲彂偒傑偡
愭偺僐乕僪婰嵹偺儖乕儖偱尒傑偡偲嘊乣嘍偑懚嵼偟側偄偺偱徣棯
屻偼慡偰徣棯偱偒側偄偺偱丄婰嵹偟偰偄傑偡
尭嶰榓壒乮僨傿儈僯僢僔儏乯
尭嶰榓壒偺偙偲傪塸岅偱偼乽僨傿儈僯僢僔儏僐乕僪乿偲尵偄傑偡
偱偼摨偠傛偆偵尒偰偄偒傑偟傚偆
僨傿儈僯僢僔儏僐乕僪偼儖乕僩傪婎弨偵抁嶰搙+尭屲搙偱宍惉偝傟傞榓壒偱偡
傑偨堦棗偱尒偰傒傑偡偲
儖乕僩亖僪
抁嶰搙亖儈侒
尭屲搙亖僜侒
偲側偭偰偄傑偡偹
偙偺榓壒偼儅僀僫乕僐乕僪偺僜偺壒偑僜侒偲敿壒壓偑偭偨偩偗偱偁傞偙偲傪
妋擣偟偰偍偄偰偔偩偝偄
偙偺榓壒偼昞婰偺巇曽偵傛偭偰屇傃曽偑曄傢傞偙偲傕偁傞柺搢側榓壒偱偡
捠忢偼僨傿儈僯僢僔儏傪堄枴偡傞彫暥帤偺dim傪偮偗偰
Cdim偲彂偒
C僨傿儈僯僢僔儏偲屇傇偙偲偑懡偄偺偱偡偑
Cm偺屲搙偺壒傪敿壒壓偘傞偲偄偆堄枴偱-5偲偄偆悢帤傪晅偗懌偟偰
Cm-5側傫偰彂偒曽傪偡傞偙偲傕偁傝傑偡
偙偺応崌傕僨傿儈僯僢僔儏偲屇傋偽峔傢側偄偺偱偡偑
堦斒揑偵偼偙偺彂偒曽偑偝傟偰偄傞帪偼
C儅僀僫乕僼儔僢僩僼傽僀僽
側傫偰屇傃曽傪偟傑偡
婰嵹儖乕儖偱偄偆側傜偽
嵟弶偺Cdim偺曽偼
嘆偲嘇傪婰嵹偟偰
嘊乣嘍偼懚嵼偟側偄偺偱徣棯
屻幰偺Cm-5偺曽偼
嘆偲嘇偱Cm偲昞婰偟
嘊乣嘋偼懚嵼偟側偄偺偱徣棯偟
嘍偱-5偲昞婰偟偰偄傞傢偗偱偡
憹嶰榓壒乮僆乕僌儊儞僩乯
憹嶰榓壒偺偙偲傪塸岅偱偼乽僆乕僌儊儞僩僐乕僪乿偲尵偄傑偡
傑偨摨偠傛偆偵尒偰偄偒傑偟傚偆
僆乕僌儊儞僩僐乕僪偼儖乕僩傪婎弨偵挿嶰搙+憹屲搙偱宍惉偝傟傞榓壒偱偡
儖乕僩亖僪
挿嶰搙亖儈
憹屲搙亖僜#
偲側偭偰偄傑偡偹
偙偺宍偵偮偄偰傕儊僕儍乕僐乕僪偺僜偺壒偵#偑晅偄偰偄傞偩偗偱偁傞偙偲傪妋擣偟偰壓偝偄
僨傿儈僯僢僔儏摨條偵偙偺榓壒傕昞婰曽朄偵傛偭偰屇傃曽偑曄傢傞偙偲偑偁傞榓壒偱偡
捠忢偼僆乕僌儊儞僩傪堄枴偡傞彫暥帤偺aug傪偮偗偰
Caug偲彂偒
C僆乕僌儊儞僩偲屇傇偙偲偑懡偄偺偱偡偑
C偺儊僕儍乕僐乕僪偺屲搙偺壒傪敿壒忋偘傞偲偄偆堄枴偐傜
C+5側傫偰彂偒曽傪偡傞応崌傕偁傝傑偡
偙偺応崌偼丄僆乕僌儊儞僩偲撉傫偱傕峔偄傑偣傫偑
C儊僕儍乕僔儍乕僾僼傽僀僽
側傫偰撉傒曽傪偡傞偙偲傕偁傝傑偡
婰嵹儖乕儖偵偮偄偰傕僨傿儈僯僢僔儏偲摨偠偱偡偹
偙偙傑偱偱丄榓壒偺拞偱傕嵟傕婎杮偵側傞庡梫嶰榓壒偺夝愢偑廔傢偭偨傢偗偱偡偑
側偐側偐慡偰埫婰偱偒傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫
摿偵墘憈傪偡傞傢偗偱偼側偄偺偱丄尒偨弖娫攃埇偱偒傞昁梫偼偁傝傑偣傫
側偺偱丄妎偊曽偺僐僣傪尵偄傑偡
傑偢儊僕儍乕僐乕僪偼C偲F偲G偺3庬椶傪妎偊偰壓偝偄
儅僀僫乕僐乕僪偼Dm偲Em偲Am偺3庬椶傪妎偊偰壓偝偄
僨傿儈僯僢僔儏僐乕僪偼Bdim偩偗妎偊偰壓偝偄
僆乕僌儊儞僩偼Caug偩偗妎偊偰壓偝偄
榓壒偼儖乕僩偐傜偺嫍棧偱庬椶暘偗偝傟偰偄傞偺偱
儖乕僩偑敿壒偁偑傟偽丄懠偺壒傕帺摦揑偵敿壒偁偑傝傑偡
偮傑傝丒丒丒弴斣偵敿壒偢偮忋偘壓偘偡傟偽栚揑偺僐乕僪偵偨偳傝拝偔偙偲偑弌棃傞傢偗偱偡
弌尰昿搙偺掅偄僨傿儈僯僢僔儏傗僆乕僌儊儞僩偼1偮偩偗妎偊偰偍偄偰
儊僕儍乕偲儅僀僫乕偼昿斏偵搊応偡傞偺偱3売強掱搙妎偊偰偍偔偲
偁偲偼傗偭偰偄傞偆偪偵妎偊傛偆偲偟側偔偰傕彑庤偵妎偊傑偡
偝偰丄師夞偼庡梫嶰榓壒埲奜偺榓壒傪堦婥偵慡晹傗偭偰偟傑偄傑偡
儊儌偺弨旛傪朰傟偢偵乣